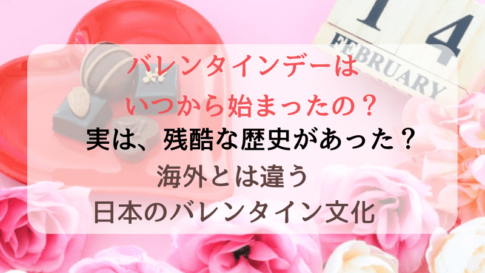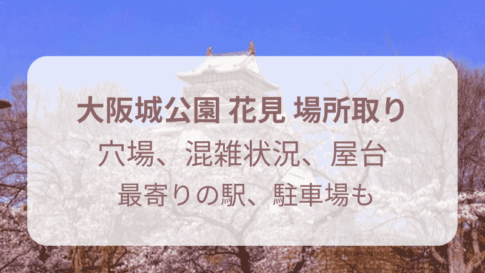京都の銀閣寺の正式名称は「慈照寺」といい、室町幕府8代将軍「足利義政」が造営したお寺です。
銀閣寺は室町時代後期に隆盛した東山文化の代表的建築と枯山水の庭園が有名ですね。
京都観光に行けば、金閣寺や銀閣寺は必ず訪れると思います。
1994年に世界遺産に登録されていますしね。
銀閣寺に訪れて疑問に思うことはありませんか?
銀閣寺なのになぜ銀箔が貼ってないのだろうと思いますよね。
私は大阪に住んでいるので、銀閣寺にはよく行きました。
その度に、どこが銀なんだろうと不思議に思いましたが、調べることもしないまま、銀閣寺に行かなくなってそのまま忘れていました。
今回は、銀閣寺は銀箔じゃない理由!銀ではないのになぜ銀閣寺と呼ぶのか?と題しまして
- 銀閣寺は銀箔でない理由!
- なぜ銀閣寺と呼ばれるのか?
についてその理由をお伝えしていこうと思います。
それではさっそく本題に入っていきましょう!
銀閣寺は銀箔じゃない理由!

出典:観光エリアガイド
結論から言うと、外壁には銀箔が貼られた痕跡がないと言うことです。
銀閣寺に銀箔が貼られていない理由!それは諸説いろいろあります。
①「幕府の財政事情により叶わなかった」
②「銀箔を貼る予定であったが、その前に義政が他界してしまった」
③「銀箔を貼らずとも、外壁の黒漆が日光の加減で銀色に輝いて見えたから」
④「当初は銀箔を貼っていたが剥がれ落ちてしまった」
⑤もともと銀箔を使う予定がなかった
などなど。
「幕府の財政事情により叶わなかった」…というのは話としては面白いですね。
「造営当初から銀箔など張る予定は無かった」というのが事実です。
これまで様々な憶測が飛び交っていましたが、実は2007年に行われた科学調査によって事実が明らかになりました。
外壁には銀箔が貼られた痕跡がないことが、この調査で判明しました。
当時の人も銀が曇ってしまう、銀泥などは真っ黒になってしまうことを知っていたので最初からそんな計画はなかったのではないでしょうか?
なぜ銀閣寺と呼ばれるようになったのか?

出典:観光エリアガイド
正式名は慈照寺なのですが、銀閣寺と呼ばれるようになったのは、江戸時代からなんです。
由来は、足利義満の建立した金閣寺に対して呼ばれるようになったとか。
銀閣寺のお庭には錦鏡池(きんきょうち)という池と「銀沙灘」(ぎんしゃだん)に「向月台」(こうげつだい)と称される2つの砂盛りがあります。
この砂盛りは月の光を本堂に照らす役割があるとされているのですが、その光った姿が月明かりで銀色に輝くようだったことから「銀閣寺」と呼ばれるようになったと言われています。
まとめ出典:観光エリアガイド

出典:観光エリアガイド
今回は、銀閣寺は銀箔じゃない理由!銀ではないのになぜ銀閣寺と呼ぶのか?と題しましてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか?
- 銀閣寺の正しい名称は、慈照寺・観音堂で、東山文化の代表的建築と枯山水の庭園が有名な場所。1994年に世界遺産に登録されている。
- 東山文化のコンセプトは、禅と簡素な文化。
- 建設は室町時代8代将軍・足利義政
- 銀閣寺のモデルは金閣寺の舎利殿。
- 銀閣寺は政治よりも文化を愛する足利義政の現実逃避の場所で、山荘がコンセプトだった。
- 銀閣寺という名は、江戸時代に発生。金閣寺に対比してそう呼ばれるようになったとされている。
- 銀閣寺に銀箔が貼られていない理由については、様々な諸説が飛び交っていた。
- 2007年の科学調査によって、外壁には銀箔が貼られた痕跡がないことが判明。
- 当初から銀箔を貼る予定がなかったと考えられている。
銀閣(観音殿)は国宝。と東求堂は日本最古の書院造りで、住宅建築遺構として国宝に指定されています。
庭園(特別史跡・特別名勝)は、白砂を段形に盛り上げた銀沙灘(中国の西湖の型)や、向月台が、月の光を反射して銀閣を照らすと言われています。
庭園は見ているだけでうっとりするほど美しいですね。